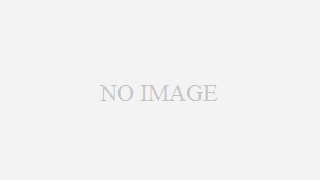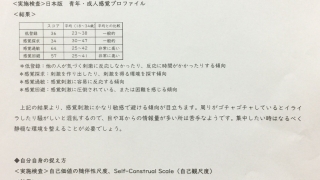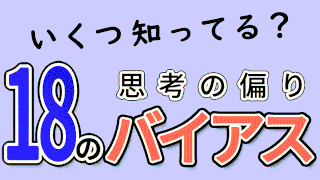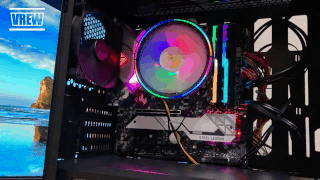※ネタバレあり
まったく予習なし、予備知識なしでなんとなくアマプラで視聴を始めたこの作品。序盤の展開が少し説明不足なままモッタリしてて、眠くなったけどギリギリ観るのをやめずに観続けた結果、観続けるほどに良くなっていく映画だった。
まず、新しく登場人物が出てくるたびに、的確なキャスティングでしかも豪華な俳優揃いなことにボルテージは高まるし、期待を裏切らない、むしろ超えてくる迫真の演技でどんどん観てる間に価値が高まってく。
序盤は、話のスケールがやや小さく、タイムスパンも短く、なのにファンタジー要素が出てきて、「?????」となった。(本当にジャンルすら知らないまま視聴を始めた)
何をどう展開していってどう収束させるんだ?って不安になったくらい。
でも冨永愛さんが出てきたらへんから身を乗り出した。物語のスケールとタイムスパンが一気に拡張された驚きと、なんか懐かしいような既視感(後述)とで、不思議な気持ちになった。
主人公の少女は、現代の子どもという設定で見れば、「そりゃそんなヘヴィな運命を一方的に背負わされたら厭世観MAXにもなるよね……」と共感できるシーンやセリフが多かったけど、いまアラサー、アラフォーの人たちが自分らの過去と置き換えて考えたとして、もし同じ境遇だったら「こんなにもワクワクする設定ないでしょ!」と思うんじゃないかな~と感じた。
予知夢みたいなものの中で自由に行動できて、その行動が現実に影響を及ぼして、なんなら地球の運命を左右するなんて、『涼宮ハルヒ』というふた昔前のアニメがシリアスに実写化したくらいの万能感あって、みなぎる人多い気がする。
なんだかんだ最後まで観て、エンドロールが始まった瞬間に、このエントリーのタイトル回収である「血の気が引くほどの感動」を覚えた。前述した「懐かしいような既視感」の正体が明らかになったから。紀里谷和明監督の作品だったことをエンドロールで初めて知った……本当に全く予習なしだったから驚いた。
「好きな邦画を3つ挙げてください」と言われたら、間髪入れずに食い気味で、
- CASSHERN
- 告白
- パコと魔法の絵本
と即答する。10代後半~20代前半の頃は、洋画・邦画を問わず、劇場・DVDを合わせて年に100本は映画を観てたけど、ぱっと頭に浮かぶ邦画はこれら3本。(後者2本が同じ監督だということをいまさっき知ったのは内緒の話)
CASSHERNは、原作もアニメも知らないまま、映画公開当時の恋人に誘われるまま劇場に観に行った作品。たぶんテーマソングが宇多田ヒカルさんだったからという理由でチョイスしたんだろうけど、思い出補正を抜きにしても衝撃を受けた映画だった。
その時の感覚が、冒頭から何度も書いてる「懐かしい既視感」となってたことが鳥肌モノ。
要はこの『世界の終わりから』を、
- 偶然アマプラで見つけて、
- 何も知らず観て、
- 既視感を抱いて、
- 最後に既視感の理由が判明する
というこの華麗なるコンボそのものがドラマチックだしクライマックスで、血の気が引くほどの感動に変わった。ネトフリでもレコメンドのマッチ度は低かったし、ネット上でCASSHERNを観たことは一度もないからサジェストでもない。本当に偶然が偶然を呼んだ奇跡体験だった。
ここからはストーリーの内容に触れようと思う。
「運命論」───哲学が好きな人や、知能指数が一部突出していてかつ内向的な人なら一度は深く考えたことがあると思う。何もかもがすべてもともと決定されているとしたら……という観点。どんな喜劇も悲劇も、些細なことも壮大なことも、過去も未来も、最初から決まりきっているんじゃないか、という視点が運命論。この運命論を軸に歴史改変とタイムパラドックスが描かれてる。『世界の終わりから』は端的に表現するとそんな映画。
世界最後の日がわりと近い未来に訪れることがわかって、その未来を変えられる可能性がある時、どう生きるかという問いは、別に物語の中だけじゃなくて現実の誰しもに当てはまることだと感じる。
アートやエンタメという点で凝った設定にしてストーリーを壮大にしてるというだけで、現実の個々の「死」にも当てはまる。人生100年時代と言われて久しいけど、5分後に車にはねられたり急性の心不全や脳梗塞になったり天災が起きて死ぬ可能性なんて全員に常に孕んでるから。
これは自身が生まれる前から生まれた後も生死の境を何度もさまよったことと、身近な人の病死や事故死や自傷・自殺などに人より少し深く関わった人生だったことで理解したことだけど、僕らは常に死とともに生きてる。隣り合わせという意味じゃない。隣り合わせどころか、裏表。常に同時進行。例外がない。
ミクロで考えれば細胞は常に死に続けてるし、共生微生物による代謝も無数に行われていて、マクロで考えれば僕らは宇宙の一部で時空間に溶け込んでいて、「死の中に生きてる」とも言える。(睡眠中の意識の行方を考えた時に、悪魔の証明を前提にすれば時空間と一体化してると解釈できることから)
つまりすべての生き物にとって死が特別なことではなく、なんなら「おともだち」くらい身近な存在だから、死を抜きに生を語ることで矛盾が生じて、矛盾が原因で「すべての現象が問題化し得る」ということ。
多くの人間は過去の歴史でも現代でも死を特別視してるから、死を忌み嫌ったり、恐怖したり、はたまた渇望したり、憧れたりする。まるでこの瞬間の主観(意識)と死との間に、途方もない距離が生じてるが如く捉えてるように僕からは見える。その矛盾こそが人生を苦悩や苦難に満ちさせてる根源なのに。
『世界の終わりから』の主人公も同じで、運命を恨んだり嘆いたり避けようとしたりするということは、運命を非日常と捉えてるからこそ感傷的・悲観的・大袈裟に捉えてしまうということ。世界最後の日も個々人の死も、なんら特別じゃないと知ると、「生きる」ということにフォーカスできるようになる。運命論がどうとかはこの瞬間の主観の感情や感覚には大して関係がないから。
もう少し突っ込むと、誰しもが自分という意識を「主人公」に据えて、自分が世界の中心かのように取り乱したり絶望・失望・落胆をしたりと右往左往しがちだけど、意識=自分と定義した時に、自分が森羅万象を構成する部品の一部なんだとわかれば、
- 部品としての存在の価値が極大であること
- どうしようもないほど自由であること
に気づく。
存在してることがゴールで、生死すら自由で、宇宙の果てだろうがいまいる場所だろうが、なんならあの世もこの世もなく、すべてが「此処」だから、ド安定、不変、永遠。この絶対的な安心感を得ることができればこそ、人間は日々を具体的に幸せに向かって変えていく勇気や行動力が備わる・漲る・湧き出る───そんな再認識をさせてくれた『世界の終わりから』、とてもいい映画だった。
CASSHERNで不完全燃焼感があったEDを、この作品で伏線回収・昇華したようなストーリーで、しかも時代にマッチするシンプルさが、相乗効果でとてもエモかった。
『世界の終わりから』
Amazonプライムビデオで観る
Netflixで観る